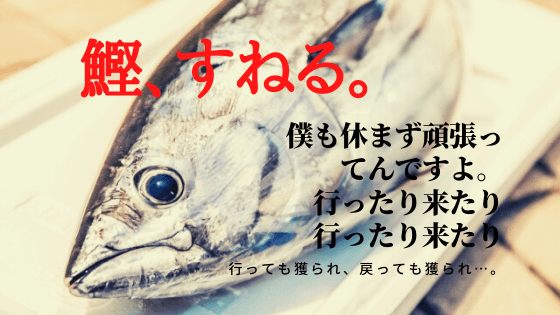どうも、ハマちゃんです。今回は1年の内2度旬を迎える「鰹」について解説します。
鰹に注目が集まるシーズンは1年のうちに2度あります。
皆さんも聞いた事があるかと思いますが、“初鰹”と呼ばれる春先にシーズンを迎える鰹と、“戻り鰹”と呼ばれる秋口にシーズンを迎える鰹。どちらも季節を感じることのできる食材として重宝されます。
そんな鰹ですが、実際にシーズンによってどんな違いがあるのか。又その生態や、有名産地、漁獲方法などについてもご紹介していきたいと思います。
まずは鰹についてどんな魚なのか特徴を押さえていきましょう。
目次
鰹の特徴や種類を知る
鰹について解説の前に鰹にどんな特徴があり、どんな見た目なのか見ていきましょう。

鰹の呼び名
地方名などが数多く存在する事や、カツオと名のつく魚との区別をする為に呼び名がいくつかあります。
ホンガツオや、真ガツオと呼ばれる事が多いです
鰹の漁獲サイズ
大型のものは1m程に成長するが、漁獲が多いのは40㎝程のものが多いです。
鰹の模様
生きてる間は興奮すると腹側に横縞が浮き出るが、死ぬとその模様は消え縦縞が現れる。
この写真でもわかるように、背中側の肌は濃い藍色で、腹側は銀色をしています。体の形はマグロのような紡錘型で尾鰭以外のヒレは小さい。鱗は頭から背中を中心にその部位だけにある。
他のカツオとの違いは腹側に出る縞模様が出るか出ないかや、顔付きの違い、模様の入り方の違いなどで区別できる。
その他の鰹の種類を紹介
スマガツオ
東京ではスマガツオ、西日本ではヤイトガツオなどと呼ばれます。行動の仕方が普通のカツオと違います。大群での行動はせず、単独もしくは小さな群れで行動している為、安定した漁獲は見込めません。
単独で行動する場合、カツオやハガツオの群れに混じって回遊しているとも言われております。
違い❶ー背中側の模様が違います。背中側に不規則渦巻いたような模様(サバに近い)がある。
違い❷ー腹側の模様が違います。カツオにある縦模様はなく、黒い斑点がいくつかあります。
違い❸ー身質が違います。脂が多くマグロに近い身質であると言われています。
ソウダガツオ
ソウダガツオと呼ばれる種類のカツオには2種類存在し、マルソウダ、ヒラソウダと区別します。両者の違いは体高の長さの違いと、鱗のある部分の違いです。
マルソウダ ー マルソウダの方が体高短く、鱗のつき方が長い。
(尾びれの手前まで)
ヒラソウダ ー ヒラソウダの方が体高が長く、鱗のつき方の方が短い。
(第二背ビレの手前まで)
違い❶ー腹側の模様が違います。カツオは腹側に縦模様が入るが、その模様はありません。
又、スマにある黒い斑点もありません。
違い❷ー血合の量が多いです。血合の量が多い為、あまり生食向きではないと言われます。
ハガツオ
名前に歯がつくようにカツオに比べて歯が大きく、やや細身で顔が大きい。ハガツオを狙った漁はほとんどなくカツオやサバなどに混じって漁獲される。
行動もカツオと似ており、季節的な回遊をする。
違い❶ー背中側の模様の違いです。カツオは腹側に縦模様が入るのに対して、ハガツオは背中側に縦模様が入る。
違い❷ー歯の違いです。歯が鋭く大きい。その為カツオに比べて下顎が大きく全体的に顔が大きいです。
様々なカツオがいますが、その違いの多くは模様にでてきます。その特徴を覚えておけば、見分けがつきますね。
さて、ここから本題のカツオについて見ていきましょう!!
鰹の生態について
カツオの生態についてですが、カツオは全世界の熱帯、温帯の海域に生息しています。日本では太平洋側に多く存在し、日本海側で水揚げされる事は稀です。
皆さんもご存知の通り、カツオは回遊魚であり季節ごとに北上と南下を繰り返します。その習性の特徴をとらえて漁も行われ、春に北上するカツオの事を“初鰹”、秋口に南下するカツオの事を“戻り鰹”と言います。
又カツオは群れを作って回遊する習性がありますが、実はその群れにも種類があるようなのです。その群れの特徴が漁をする上での重要な手かがりにもなったりします。いくか紹介しましょう。
| 素群 | “すなむら”と言い、この群はその他の物にお供しておらずカツオだけで群を作っている群れの事を指します。 |
| 鳥付 | “とりつき”と言い、餌を横取りしようとする海鳥がその群れの上を飛んでいる状態の群れの事を指します。この海鳥の有無を見て漁船がカツオ郡を探す手かがりにします。 |
| 鯨付 | “くじらつき”と言い、外敵から身を守るために、ジンベエザメや鯨に身を隠しながらサメや鯨と共に行動している群れの事を指します。 |
| 木付 | “きつき”と言い、流木や漂流物の下にいる群れの事を指します。 この習性を利用してパヤオという人工漂流物を流し、それにつくカツオを漁獲する漁法がある程です。 |
群れ方にも特徴があり、面白いですよね。
上記の他に沿岸水の影響が少なく、水温が高く、天然の餌が豊富な場所に年中生息する瀬付と言われる群れなども存在するようです。
先ほど日本海で水揚げされるのは稀と書きましたが、水揚げされる事もあります。
その鰹のことを巷では“迷い鰹”と言い、近年注目を浴びています。
本来北上するルートを外れ、対馬海流にのって日本海へ迷いこんだ鰹の事を指します。
日本海の豊富な餌と冷たい海域で成長する為、身が締まり身質と脂の乗り方が別格と言われます。気になる方はぜひ調べて見てください!!!
鰹の旬について
ここからは鰹の旬についてです。
前述しましたように群れを作りながら回遊をするカツオですが、一般的には日本列島沿いを黒潮にのって北上し、南下すると言われております。
しかし、それは分かりやすく回遊パターンを表現したにすぎず、実際には北上ルートは様々であるとされています。その様々なルートから春から夏にかけて日本近海に北上してきたカツオを初鰹と言います。
この時期のカツオは熱帯海域から北上してくる為、戻り鰹に比べると脂が乗っておらずさっぱりした味わいと、もちっとした食感が特徴です。
熱帯海域は魚の産卵や孵化には好ましいが、魚が大きく成長する為の餌は少ないと言われております。
日本近海まで北上してきた鰹は、餌の豊富な黒潮と親潮のぶつかる海域から親潮海流を回遊しながら餌を食べ、秋口に南下を始めます。
この時期のカツオを「戻り鰹」と言い、脂がのり初鰹とはまた違う味わいを楽しめます。
脂がのっている事からトロガツオとも呼ばれます。
鰹の生態から特徴をとらえ1年の内に2度の旬を楽しむ事ができ、季節を感じれる。日本人にとって馴染みの深い鰹の生態と旬についてなんとなくお分かり頂けたかと思います。
鰹について(まとめ)
ここまで記事をご覧いただき、ありがとうございました。鰹の回遊の仕方や群れの作り方など面白いですよね。
日本列島は縦に長い為、時期によって初鰹の獲れ始め、又鰹の南下の進み具合から戻り鰹の若干の旬のズレはあると思います。
又北上ルートや、南下ルートも何パターンかある為、漁場によって多少の個体差が出るのではないかと思われます。水揚げの時期や、産地を知ると食べずともどんな鰹なのかイメージできるかもしれません。
ぜひいろんな時期のいろんな産地の鰹を食べて見てください!!!
では、この辺で。